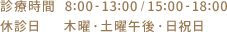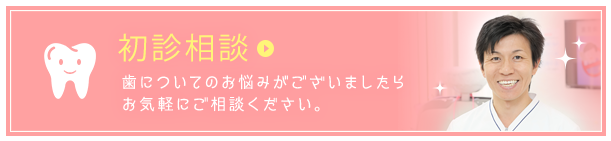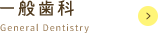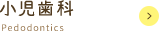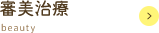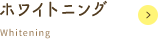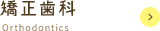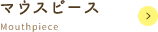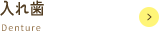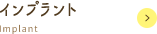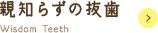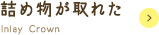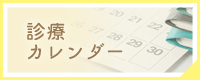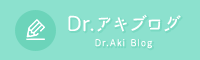大学病院と同等の治療が可能

一番奥に、一番最後に生えてくる歯が親知らずです。
日本人は比較的あごが小さい方が多いため、最後に生えてくる親知らずは、正しい歯並びで生えてくることができないことが多くあり、このため正しいかみ合わせにならなかったり、前の歯を押してしまったりとトラブルになることがあります。
また、正しく生えていたとしても、きちんと歯みがきをして健康に維持することが難しいため、親知らずだけでなく、その前の歯がむし歯や歯周病になってしまうリスクもあるため注意が必要です。
当院は、CTをはじめとした検査機器や、オペ専用の個室を完備しているため、大学病院と同等の治療が行えます。他の歯科医院では抜けないと診断された方も、お気軽にご相談ください。
親知らずとは

親知らずは、現代の食生活の変化に伴い、顎が小さくなり、完全に生えてこないことが珍しくありません。原始時代には、顎のサイズが大きく、他の大臼歯と同様にまっすぐに生え、使用されていましたが、現代では軟食中心の食生活の影響で顎が小さくなり、最後に生える親知らずはスペースが不足し、斜めや横に生えることが増えています。
位置異常で不完全に生えた場合、歯ブラシでの手入れが難しく、汚れが溜まりやすくなります。その結果、むし歯が発生し、痛みや腫れを引き起こすことが多いです。
このような場合、炎症(智歯周囲炎)を併発することが多く、根本的な治療として抜歯が必要になります。稀に、智歯周囲炎を放置すると、首や胸部に炎症が広がり、蜂窩織炎(ほうかしきえん)を引き起こし、緊急入院や気管切開、さらには命に関わる事態になることもあります。
抜いた方がいい親知らず
1.智歯周囲炎(ちししゅういえん)
「親知らず」の周囲が腫れ、炎症を引き起こす症状です。
2.親知らずの痛みや腫れが見られる
親知らずが半分しか出ていないため、十分にブラッシングができず、汚れが蓄積し、むし歯や歯周病を引き起こす可能性があります。また、出るスペースがないために歯ぐきに覆われ、そこに細菌が侵入して炎症を引き起こすこともあります。
3.歯並びに異常が生じる
親知らずが生えてくることで、前の歯を押し、歯並びが悪化することがあります。前歯の叢生が強くなることもあります。
4.前の歯がむし歯になるリスク
親知らずがむし歯になると、その前の歯もむし歯になる可能性があります。また、前の歯の根が親知らずに押されることで、押された歯の根が溶けてしまい、抜歯が必要になることも少なくありません。
5.口臭の原因となる
親知らずの部位は歯ブラシが届かず、クリーニングも行えないことが多いため、口の中が常に不潔になり、口臭の一因となります。
6.顎関節症を引き起こしやすい
上あごと下あごのかみ合わせる歯がどちらか一方だけ欠けている場合、歯が伸びてきてあごの動きを妨げ、関節に痛みを引き起こすことがあります。また、親知らずの異常な生え方によって歯並びやかみ合わせが悪化すると、あごの関節に負担がかかり、あごの痛みや口が開けにくくなるなどの症状が現れることもあります。
当院の親知らずの抜歯

痛みに配慮した治療
当院では、患者様ができるだけ痛みを感じない治療法を採用しています。患者様の快適さと安心感を最優先に考慮したアプローチにより、ストレスの少ない治療体験を提供いたします。

低侵襲でスムーズな抜歯
当院の抜歯手法は低侵襲であり、術後の腫れを最小限に抑えることを目指しています。これにより、患者様の回復が迅速で、日常生活への影響を最小限に抑えることが可能です。

カウンセリングを重視した治療
常に患者様の意見に耳を傾け、そのニーズや不安を理解することに努めています。これにより、患者様一人ひとりに適した治療プランを提供します。
親知らずの抜歯の流れ
親知らずの抜歯の流れ
-
1.検査
CT撮影を行い、親知らずや骨の状態を調査します。 特に、歯が歯茎に埋まっている埋伏歯の場合、安全な治療計画を立てるためにCT撮影は必須です。
-
2.治療計画の説明
治療計画に関して、写真などを使用して現在の状況や将来的な影響を詳しく説明いたします。 もし抜歯が必要と判断された場合には、治療計画についても併せてご説明いたします。
-
3.親知らずの抜歯
歯の状態によって異なりますが、身体への負担や感染症のリスクを考慮し、できるだけ短時間で治療を行うよう努めます。 麻酔を使用しますので、治療中に痛みを感じることはありませんので、ご安心ください。
-
4.メインテナンス
抜歯直後には、抜歯によって生じた穴(抜歯窩)が回復するための血の塊が形成されますので、食事や歯みがきに関する注意点について説明いたします。 抜歯が他の歯に与える影響や口全体の健康を考慮し、定期的なメンテナンスを推奨いたします。